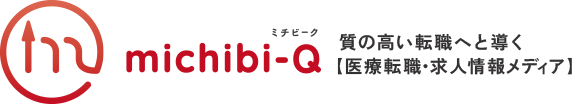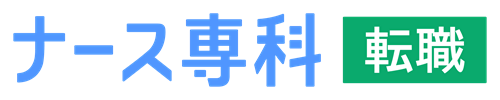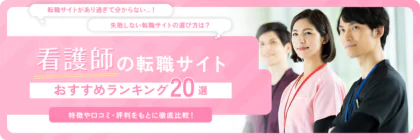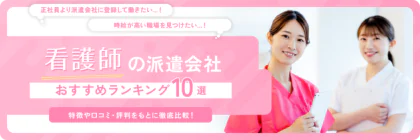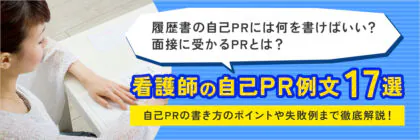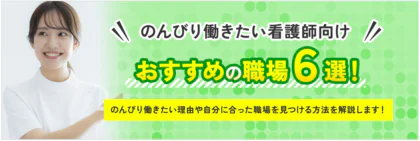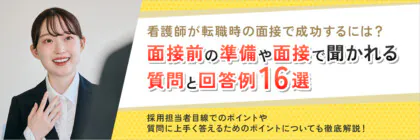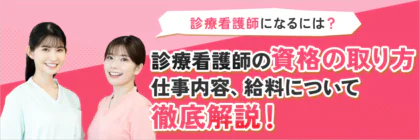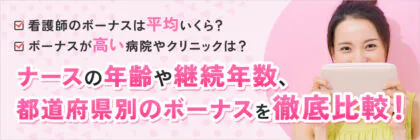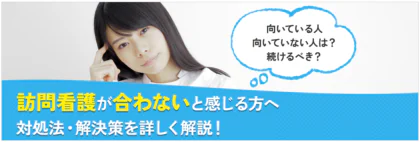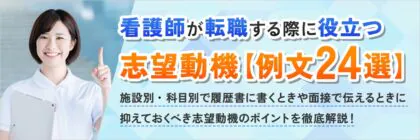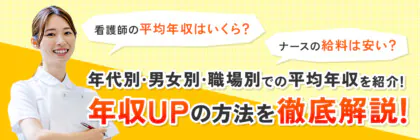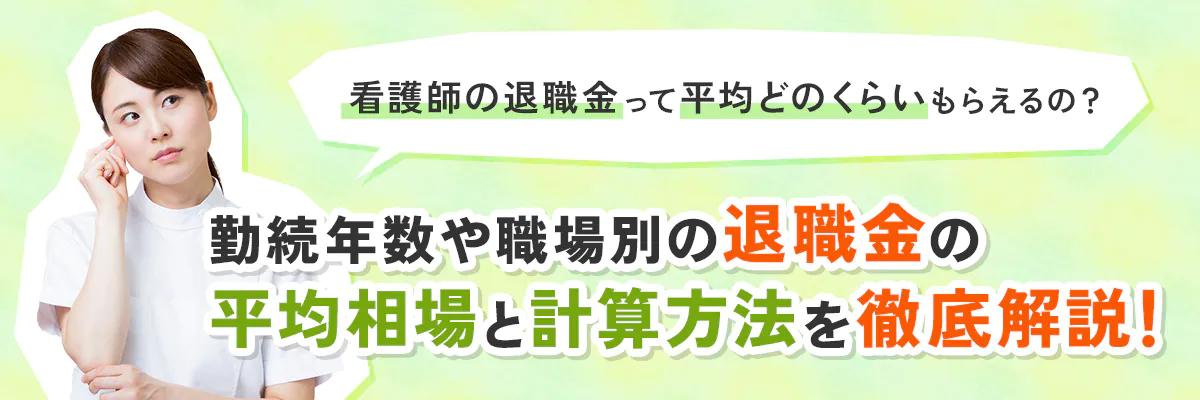
※当サイト(ミチビーク)はアフィリエイト広告を掲載しています。
この記事の監修者

【経歴】
2016年に看護師免許を取得した後、総合病院での勤務を経験。循環器内科、呼吸器内科、肝臓内科、腎臓内科、代謝科など、多岐にわたる専門分野が混在する病棟での業務に従事。
【資格】
看護師

【経歴】
大学卒業後、ウェディングプランナーとして営業職を経験し、24歳からITベンチャー企業の人事部にて採用・教育などの仕事に従事。採用は新卒・中途の営業職から事務職、クリエイティブ職など幅広い職種の母集団形成から面接実施、内定者フォロー、入社手続き等を行い、教育では研修コンテンツ企画、資料作成、講師育成までを実施。人材開発部立ち上げや、社内の人事評価、従業員満足度調査、社員のメンタルケアなども行っていた。それらの経験を経て、さらに専門性を高めるためにキャリアコンサルタントの資格を取得。
現在も今までの経験・知識を活かしつつ、二児の子育てと両立させながら、株式会社Method innovationのグループ会社である株式会社ドクターブリッジにて人事の仕事に従事している。
【資格】
キャリアコンサルタント
アロマテラピー検定1級
プラクティカルフォト検定1級
ファッションビジネス能力検定1級
ファッション販売能力検定1級
【看護師におすすめの転職サイト】
さらに参考記事:【看護師向け】おすすめの転職サイト人気ランキング20選を比較|選び方や口コミも紹介の記事もぜひご覧ください!
「看護師の退職金はいったいどれぐらい?」
「看護師の退職金制度について知りたい」
「退職金は何年目くらいから支給されるの?」
「看護師の退職金は少ない?多い?」
このように退職金について不安や疑問を抱いている看護師も多いのではないでしょうか。
看護師にとって長年働いた職場からの退職金は、第2の人生をスタートするための大切な資金です。
とはいえ、退職金の金額や条件は職場ごとや勤続年数により異なり、その相場や制度、各職場の違いに関する情報は散在しています。
本記事にて、看護師が退職金について抱える疑問や不安を解決するため、相場や制度、職場ごとの違いなどを詳しく解説します。
本記事を読むことで、自身が働く職場の退職金制度や相場を知り、退職金を増やすポイントやよくある質問も紹介しますので、安心して新しい人生をスタートするための準備ができるでしょう。
看護師の退職金制度の重要性
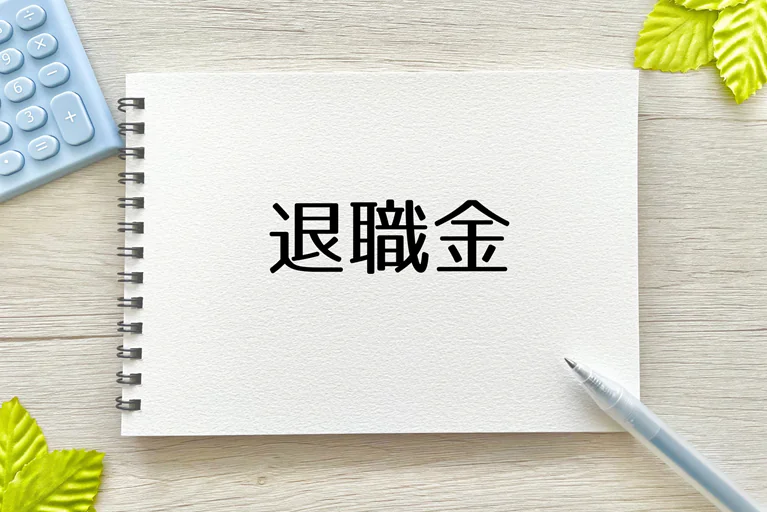 看護師にとって、退職金制度は将来の生活を支える大切な備えのひとつです。この制度は、長年にわたり医療現場で業務に従事した看護師に対して、労働の対価として一定の金額を支給する仕組みです。ここでは、退職金制度の概要とその重要性について詳しく解説します。
看護師にとって、退職金制度は将来の生活を支える大切な備えのひとつです。この制度は、長年にわたり医療現場で業務に従事した看護師に対して、労働の対価として一定の金額を支給する仕組みです。ここでは、退職金制度の概要とその重要性について詳しく解説します。退職金制度の基本的な役割
退職金制度は、いずれも看護師が長期的に安心して働くための基盤となる制度です。これらが整備されていることで、子育てや仕事との両立を図る看護師にとっても、将来設計を立てやすくなります。
看護師にとって退職金制度が重要な理由
また、主任や管理職など責任ある立場に就く看護師は、病院や施設によっては役職に応じた加算がされることもあり、制度の詳細や設けられ方は職場によって異なります。制度の有無や条件は、就職や転職時の志望動機に影響する要素にもなり得るでしょう。
病院・施設ごとの制度の違いを理解しておこう
退職金制度の有無は法律上の義務ではないため、全ての病院や施設に設けられているわけではありません。一部の医療法人や介護施設では制度そのものが存在しない場合もあり、事前に詳細を確認しておくことが必要です。
また、制度が設けられていても、支給額や条件は法人によって大きく異なります。例えば、功績倍率制度を導入して貢献度を反映させる施設もあれば、勤続年数に基づく一律支給の方式を採用している施設もあります。看護師としてのキャリアを考える上で、こうした制度の違いを把握し、自身に合った職場を検討することが重要です。
看護師の退職金の平均相場は?10年・20年でいくらもらえる?
看護師の勤続年数に応じた退職金の平均相場は、勤続期間によって受け取れる退職金額が異なることを意味します。
以下は、勤続年数による看護師の退職金の平均相場の例です。
これらの金額はあくまで平均相場であり、個人の勤続年数や労働条件によって異なることがあります。
【勤続3年の看護師の退職金】20~30万円程度

看護師の勤続3年目の場合の退職金は、多くても30万円程度が相場と言われています。
新卒の場合、勤続3年目は一人前になる時期であり、中途採用の場合、職場のやり方や雰囲気に慣れてきて戦力となる時期です。
勤続年数や職場への貢献度に応じて、退職金の金額が決まります。
職場への貢献度が低く勤続年数が短い場合、退職金は給与1ヶ月分のおおよそ30万円が目安となります。
ただし、医療機関によっては退職金制度が設けられていない場合や、支給額が30万円未満となることもあるため、注意が必要です。
【勤続5年の看護師の退職金】50万円~100万円程度

看護師の勤続5年目の場合の退職金相場は、おおよそ50万円から100万円程度です。
勤続5年目になると、一般的には一通りの業務ができるようになり、後輩の指導や責任あるポジションに就く場合があります。
医療機関によっては退職一時金制度が適用されておりますが、3年働いても支給されない場合もあります。
しかし、勤続5年目の場合、退職一時金制度が適用される職場がほとんどです。
勤続3年の退職金と勤続5年の退職金の支給額は異なります。
退職金が多ければ次の転職先までの生活費に充てられるため、同じ職場に5年以上勤めてから転職するのも選択肢の一つです。
まとまった退職金を受け取ることで、次の転職先や今後のキャリアについてゆっくり考える時間が持てます。
もし100万円の退職金があれば、およそ3か月分の生活費を賄うことができます。
転職先を探す期間や独立開業を考える場合の資金調達などに活用できるため、将来のキャリアを考えるうえで重要な資金源となるでしょう。
【勤続10年の看護師の退職金】250万円~300万円程度

看護師が勤続10年目の場合に退職する場合、その退職金の相場は約250〜300万円です。
勤続10年目の場合、新卒入社から10年以上の経験を持つ看護師が多く、一定の貢献度が期待されます。また、役職に就いている場合は、より高額な退職金を支給されるでしょう。
勤続10年目はライフステージの変化によって、転職や退職を検討する人が多い時期でもあります。
例えば、出産や育児、スキルアップのために勉強をしたいと考える人もいます。
このような場合、多くの退職金を受け取れれば、出産や育児資金、勉強費用などに充てられるでしょう。
【勤続20年の看護師の退職金】450万円~600万円程度

20年間勤務した看護師の退職金の相場は、おおよそ450〜600万円ほどです。
勤続20年になってくると、新卒で入社した場合は40歳以上でベテランの域に入ります。
この年代は子どもの教育費や老後の生活費など、お金が必要な場面が多いため、退職金の額が気になるところです。しかしながら、医療機関によっては勤続年数や役職、貢献度が退職金に反映されないこともあります。
そのため、就業規則を確認し、十分な退職金を受け取るために、早い段階で転職先を考えることが大切です。
また、定年退職まであと数年の方もいるため、自己都合退職にならないように注意が必要です。
【看護師の定年時の退職金】1,000万円以下~2,000万円程度
看護師の定年時の退職金は、おおよそ1,000万円以下から2,000万円程度です。
金額は、勤続年数・給与などによって異なります。
一般的には10年以上勤めたときには50万円以上、20年以上勤めたときには450万円以上、定年時には1,000万円以下から2,000万円程度が支払われることが多いようです。
ただし、医療機関ごとに退職金制度が異なるため、支給される金額も異なる場合があります。
看護師の職場別による退職金の平均相場
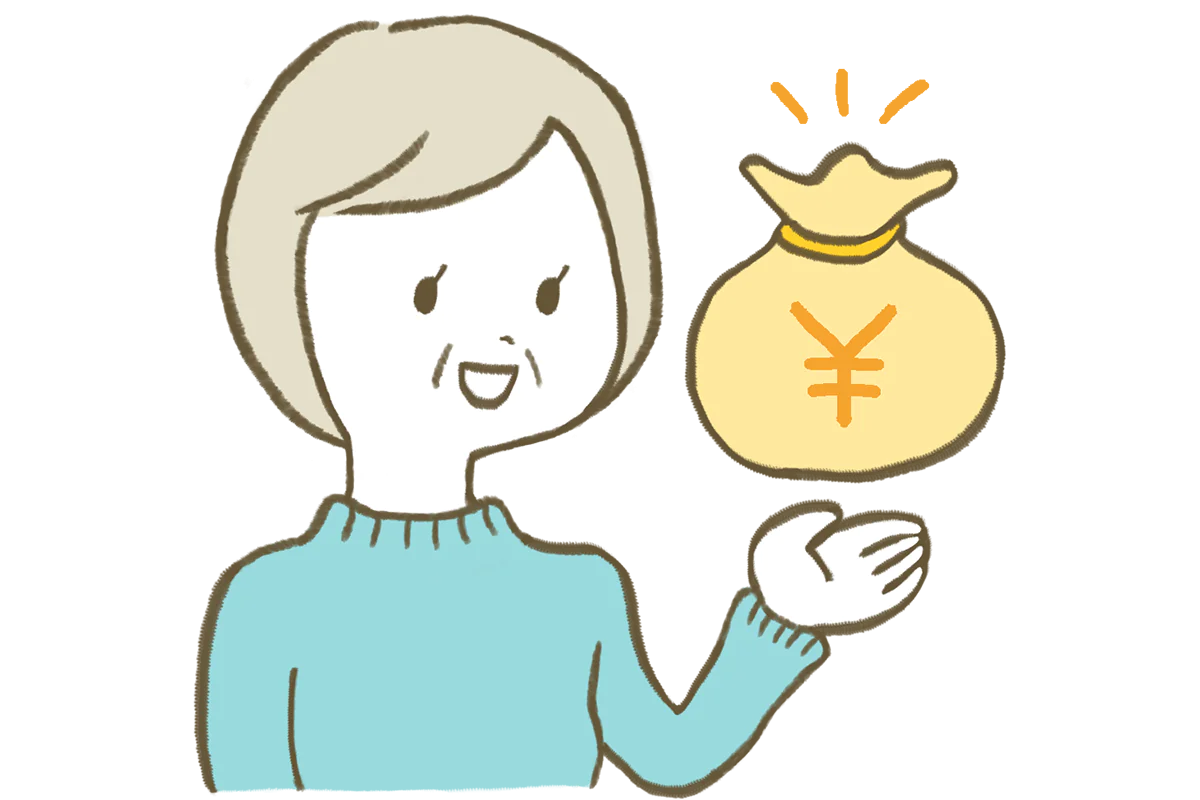
看護師の職場別に見た平均相場は、以下の通りです。
ただし、看護師の勤務先によって退職金の金額は異なります。
それぞれ解説します。
国立病院
国立病院で働く看護師の退職金の平均相場は、おおよそ1,800万円〜2,000万円程度です。
国立病院は、国が運営する医療機関であり、安定した経営基盤があることから、他の職場に比べて高い退職金が支払われる傾向にあります。
ただし、国立病院でも退職金額には個人差があるため、具体的な金額については職歴や勤務時間、年収などによって異なります。
公立病院
公立病院で働く看護師の平均相場は、おおよそ1,400万円〜1,800万円程度です。
公立病院は国が運営する病院で公務員としての待遇があるため、退職金についても公務員と同様に規定があります。
一般的には、勤続年数や給与などの条件によって退職金が決まるのです。ただし、これはあくまでも平均的な相場であり、個人の条件によって異なる場合があります。
また、公立病院ごとに退職金の規定が異なる場合があるため、詳しくは各病院の規定を確認することが必要です。
大手総合病院
大手総合病院で働く看護師の平均的な退職金は、おおよそ1,000万円から1,500万円程度です。
ただし、勤続年数や退職理由、会社の規模によって異なります。
また、個人の退職金制度や加入している年金制度なども影響する場合があります。
小規模なクリニック
小規模なクリニックにおいては、退職金の支給は義務化されていないため、支払われることは少ないと言えます。
一般的に、退職金は企業によって支払われることが多く、大手総合病院や公立病院、国立病院などの大規模な医療機関では、退職金制度が整備されていることが多いです。
ただ、小規模なクリニックでは経営規模が小さいため、退職金を支払う余裕がないことが多いとされています。
小規模なクリニックで働く場合、退職金制度が整備されていない可能性が高いため、将来的な退職金の受け取りについては、しっかりと確認しておくことが重要です。
介護関連施設
介護関連施設で働く退職金の平均相場は、おおよそ150万円から300万円程度です。
介護関連施設には、老人ホーム、特別養護老人ホーム、介護施設、グループホームなどがありますが、これらの施設における退職金の支給状況は施設によって異なります。
一般的に、介護関連施設で勤務する場合は、退職金の支給が義務付けられていません。
入社時に締結した労働契約に基づいて支給されることが多く、支給額は勤続年数や役職などによって異なります。
ただし、介護関連施設が公的な施設である場合は、公務員と同様に退職金が支給される可能性があります。
以下は、介護関連施設における退職金の平均相場の一例です。
- 老人ホーム:150万円程度
- 特別養護老人ホーム:200万円程度
- 介護施設:250万円程度
- グループホーム:300万円程度
ただし、これらはあくまでも一例であり、施設や地域によって異なる場合があります。
また、退職金の支給には労働契約や労働条件に関する法律など、様々な要因が関係してきますので、詳しい情報を知るためには、各施設に直接問い合わせることが必要です。
看護師資格による退職金の平均相場
看護師の資格により退職金の相場が異なることは広く知られていますが、具体的にはどのような差があるのでしょうか。
それぞれの平均相場を説明します。
准看護師

准看護師は看護師に次ぐ資格で、看護師の補助業務ができます。
准看護師が退職するとなった場合、以下のような支給額が算出されます。
- 基本額:月給の支給率×勤続年数×12ヶ月分
- 調整額:平均退職手当額から基本額を差し引いた額
月給が20万円で勤続年数が10年だった場合は、以下の通りです。
- 基本額:20万円×15%(支給率)×10年×12ヶ月=360万円
- 調整額:平均退職手当額が550万円であるとすると、550万円-360万円=190万円
この場合の准看護師の退職手当額は、基本額360万円に調整額190万円を加えた550万円です。
准看護師の退職金は、基本額と調整額から算出されます。
基本額は月給の支給率と勤続年数に応じて算出され、調整額は平均退職手当額から基本額を差し引いた額です。
支給額は月給や勤続年数によって変動しますが、一般的に勤続10年の場合の退職手当はおよそ550万円が目安とされています。
助産師

助産師の退職金は、勤務先や勤務年数によって変わります。
一般的には、勤続10年で約400〜600万円、20年で1,300〜1,500万円程度が平均的な相場です。
看護師は同じ期間の勤務年数でも、助産師よりも退職金の金額が低くなる傾向があります。
例えば、大規模な病院で勤務し定年まで勤め上げた場合、退職金が2,500万円以上となることもあるそうです。
具体的には、以下のような退職金が出たケースがあります。
- 10年勤続:400~600万円程度
- 20年勤続:1,300~1,500万円程度
- 大規模な病院での勤務で、定年まで勤め上げた場合:2,500万円以上
助産師はその特殊性から看護師よりも高い給与水準が求められることがあるため、比較しても高額な退職金が期待される資格と言えます。
保健師
保健師の退職金は公的な機関で働く場合が多く、公務員またはそれに準ずる扱いです。
退職金は、退職月の給料月額に支給率をかけたものに調整額を加えたもので計算されます。
公務員の退職手当は地方自治法に基づき、条例により定められています。
退職手当の計算方法及び支給率は、以下の通りです。
- 退職手当額=基本額+調整額
- 基本額=退職日給料月額×退職理由別・勤続年数別支給率
- 調整額=調整月額のうちその額が多いものから60ヶ月分の額を合計した額
基本額の支給率は、勤続年数によって変わります。
例えば、定年退職した際には、勤続35年以上で支給率は49.59ヶ月分として計算されます。
そのため、保健師の一人当たりの平均支給率は、定年退職で24,216,000円となる見込みです。
保健師は助産師と同じく、看護師の職種の中で退職金が高めに設定されている場合が多いです。
公的な機関で働く場合は公務員としての待遇が与えられるため、退職金もしっかりと支給されます。
4つの計算方法がある看護師の退職金
看護師の退職金は多くの場合、基本給をベースに計算されますが、計算方法は4種類存在します。
それぞれの方法で退職金の額が異なるため、自身の労働条件に合わせて選択することが大切です。
それぞれ解説します。
基本給ベース
「基本給ベース」とは、看護師の基本給を基準に退職金を算出する方法です。
基本給とは、看護師が雇用されている医療機関での最低給与額のことです。
基本給に勤続年数を掛け合わせることで退職金を算出し、勤続年数に応じて退職金額が増加する仕組みです。
退職金 = 基本給 × 勤続年数
具体例として、看護師Aさんの基本給が30万円・勤続20年の場合、退職金は600万円支給されます。
同様に、基本給が40万円、勤続10年の看護師Bさんの場合は、400万円が退職金として支払われるでしょう。
基本給を基準とした計算方法では、勤続年数が短くても基本給が高ければ、退職金額が多くなることが期待されます。
なお、勤続年数が長い人にとっては、勤続年数ベースや功績倍率ベースの方が有利に働くこともあります。
固定金ベース
「固定金ベース」は、医療機関が設定した固定の金額に勤続年数を乗じて計算する方式を指します。
退職金 = 固定金 × 勤続年数
勤続年数が長ければ退職金も多くなりますが、固定金額が低い場合は退職金が少なくなるのが特徴です。
一般的な相場は15万円ほどで、勤続20年の場合ですと300万円の退職金が支払われます。
ただし、固定金額は医療機関によって違いがあり、10万円ほどの場合もあります。
この場合、勤続40年でも退職金は400万円しか支給されません。
勤続年数が短い場合には退職金が支払われないことがほとんどで、3年以上働いたら退職金が支払われるのが一般的です。
また、固定金額が設定されている場合でも、昇給や役職に就いた場合には反映されないことにも注意が必要です。
勤続年数ベース
「勤続年数ベース」とは、勤続年数に応じて退職金の金額を一定の基準で決める方法です。
例えば、勤続年数ごとに定められた金額が以下の通り支払われます。
- 5年以上勤続:100万円
- 10年以上勤続:200万円
- 20年以上勤続:300万円
ただし、退職金の額は医療機関ごとに勤続年数によって異なるため、就業規則で必ず確認する必要があります。
功績倍率ベース
「功績倍率ベース」とは、基本給に勤続年数と評価に応じた倍率を掛け合わせて退職金を算出する方法です。
退職金=基本給×勤続年数×功績倍率
功績倍率は職場での貢献度に応じて変動し、その基準値は「1」と設定されています。
例えば、基本給が30万円で勤続30年として、高評価を得て功績倍率が「1.3」の場合、退職金は1,170万円が支給されます。一方、マイナス評価で功績倍率が「0.9」だった場合は、810万円と支給額が少なくなるのです。
この方法では、医療機関からの評価によって支給額が大きく異なるため、働くモチベーションを維持しやすいのが特徴です。
ただし、功績倍率の評価が不公平であったり、職場の人間関係によって左右されたりする場合もあるため、注意してください。
看護師の退職金制度は3つある
それぞれの制度には特徴やメリットがあるため、自身の希望や職場について良く確認することが大切です。
退職一時金制度
退職一時金制度とは、従業員が退職する際に、企業からまとまった金額が支給される制度のことです。
看護師の場合、勤続年数に応じて一定の金額が支給されます。
退職一時金は、長く勤務するほど支給額が増加します。
また、勤続年数が一定期間以上であることが条件となっている場合もあります。
退職一時金制度は、退職後のライフプラン設計にとって重要な要素となるため、退職前に確認することが大切です。
メリットは以下の通りです。
- 退職時に一定の金額が手元に入るため、ライフプラン設計を立てやすい
- 勤続年数が長いほど支給額が増えるため、長期的に働くことでリタイア後の生活を安定させられる
デメリットは以下の点が挙げられます。
- 勤続年数が一定期間以上であることが条件であるため、短期間での退職の場合は支給されない可能性がある
- 支給額が事前に決められているため、退職時の条件では支給額が少なくなる可能性がある
企業によって支給額や条件が異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
企業年金制度
企業年金制度とは、企業が従業員に対して退職金を支給するための制度のことです。
企業年金には、確定拠出型と確定給付型の2種類があります。
確定拠出型は、企業が従業員の退職金を積み立てるために毎月一定額を拠出する方式です。
一方、確定給付型は、企業が従業員の退職金を予め決められた基準に基づいて支給する方式です。
企業年金制度においてのメリットは、従業員が定年退職した際に一定の退職金が支払われるため、安心して老後を迎えられる点です。
また、企業が従業員の退職金を一定額積み立てるため、従業員の負担が軽減される点もあります。
一方、企業年金制度のデメリットは、企業が経営状況によっては従業員の退職金を支払えなくなる可能性がある点です。
また、確定給付型では企業が支払う退職金が保証されているわけではないため、少なくなる可能性もあります。
企業年金制度は、従業員にとっては老後の安心のために有用な制度ですが、企業にとっては負担が大きい面もあるため、導入するかどうかは慎重に検討する必要があります。
前払い制度
企業によっては、「前払い制度」という退職金の支払い方式を採用しているところもあります。
この制度では、現役期間中にあらかじめ決められた金額が毎月の給与や賞与に含まれて支払われます。
そのため、退職金を貯めるために計画的に行動する必要があります。
ただし、基本給が高く設定されている場合には、この制度を採用している可能性が高いため、一時支給や定期支給がないことに注意が必要です。
在職中に自分で資金を管理・運用できるため、前払い制度には資産を増やせるメリットがあります。
投資に取り組む人が増えている昨今、自分で商品を選んで老後資金を確保することも可能です。
現在は手軽に始められる資産運用商品が多く、税制面での優遇が受けられるケースもあります。
それらの商品をうまく利用することで、お得に資産形成ができます。
看護師は退職金がもらえない場合がある?
看護師の退職金について、不安を持つ方も多いかもしれません。
ただし、現実には看護師が退職金を受け取れないケースもあります。
看護師が退職金を受け取るための条件や、退職金が支給されやすい職場について解説します。
退職金の導入について
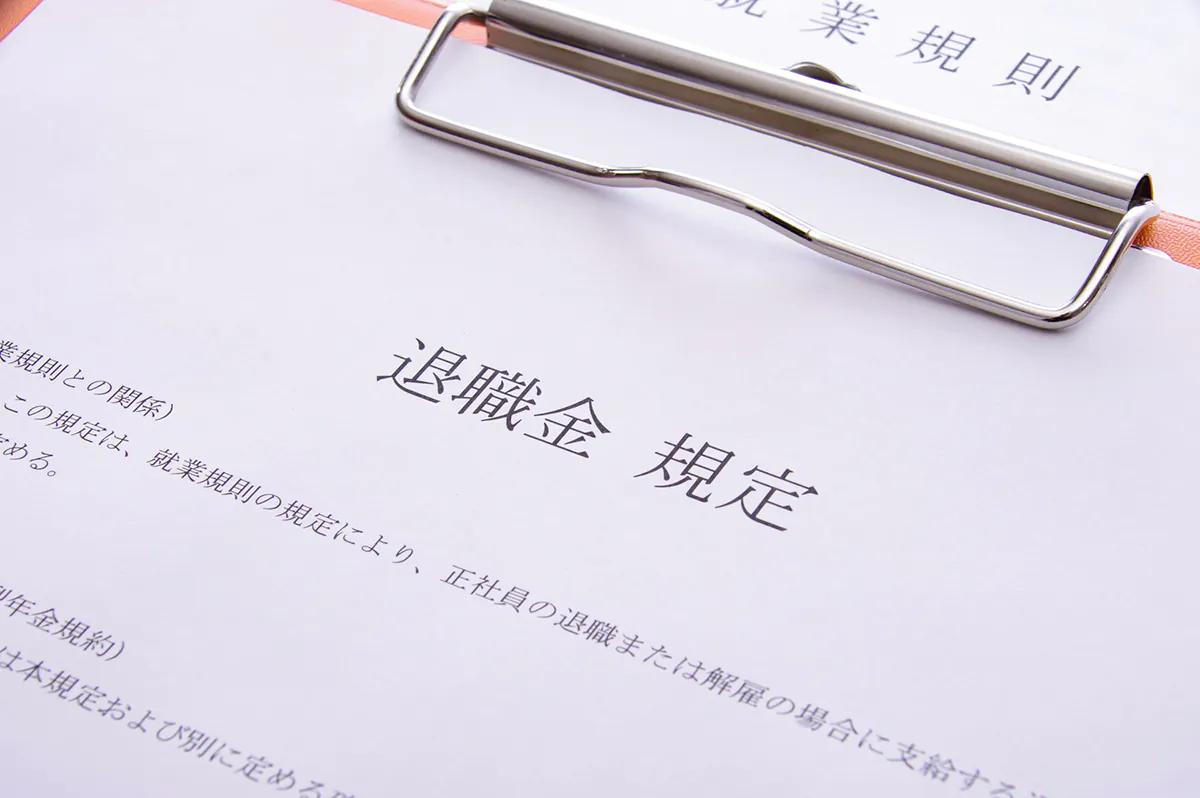
退職金は、企業によって異なる制度が設けられているため、看護師が働く職場によって導入の有無が異なります。
しかし近年、看護師の退職金制度に対する関心が高まり、制度を導入する医療機関が増えています。
医療・福祉業界全体で退職金制度を取り入れている割合は、厚生労働省の「平成30年就労条件総合調査」によると87.3%が制度を採用しています。
公的病院や大手民間病院、大手介護施設などは、退職金を導入していることが多いです。
一方、退職金が導入されていない職場としては、小規模なクリニックや介護施設、個人経営の病院などが挙げられます。
このように、その制度や支払額は病院や施設によって異なります。
しかし、退職金制度の改革も進んでおり、将来的には代替となる制度が導入される可能性もあります。
退職金がある可能性の高い職場
退職金がある可能性の高い職場には、一般的に公務員や大手企業が挙げられます。
これらの職場では、社員の退職金制度が整備されていることが多く、入社時には退職金の支払いが確約されていることもあります。
公務員の場合、国や地方自治体が退職金制度を設けており、勤続年数に応じた一定の支給が保証されています。
また、大手企業でも、一定の勤続年数を満たした社員には退職金が支払われることが一般的です。
退職金がある職場は、将来の安心感を得るためにも魅力的です。
退職金制度が整備されているかどうかは、就職先を選ぶ際に重要なポイントの一つです。
退職金がない可能性の高い職場
退職金がない可能性の高い職場とは、中小企業や非正規雇用の場合が多いです。
中小企業では、経営者の経済状況によっては、退職金を支払えない場合があります。
また、非正規雇用の場合、退職金が支払われないことが多く、短期のアルバイトや派遣社員などは特にその傾向が強いです。
退職金が支払われない理由は様々ですが、中には以下のようなケースが挙げられます。
- 経営規模が小さいため、財務的余裕がない
- 職金制度を導入するための法的手続や手間がかかる
このような理由から、退職金がない可能性が高い職場では入社前にしっかりと確認することが重要です。
具体例として、個人事業主が経営する小さなクリニックや飲食店、またはスタートアップ企業などが挙げられます。
これらの職場では、社員数が少なく財務面が厳しい場合が多く、退職金が支払われない可能性が高いです。
退職金の有無は労働者にとって重要な問題ですので、就職活動の際には、企業の福利厚生についてしっかりと確認することが大切です。
国家公務員看護師は1年目から退職金がもらえる!計算方法は?

国家公務員看護師は勤続年数に応じて退職金をもらえます。
さらに、国家公務員は一定期間勤務しただけで退職金がもらえるため、看護師でも1年目からもらえます。
では、具体的に国家公務員看護師の計算方法はどのようになっているのでしょうか。
以下は、「国家公務員の退職金」と「地方公務員の退職金」の計算方法を詳しく説明します。
国家公務員の退職金
国家公務員の退職金は、国家公務員法によって規定されています。
退職手当額の算出方法は以下の通りです。
退職手当額 = 退職日の基本給(俸給月給) × 退職理由別・勤続年数別支給率
基本給の俸給月給は職種によって異なるため、人事院が定めた俸給表に基づいて算出されます。
例えば、看護師の平均俸給額は317,928円であり、この金額は平均年齢47.3歳の俸給額です。
ただし、勤続年数が長い場合や定年後に退職する場合は、俸給額が増えることがあります。
退職理由別や勤続年数別の退職手当支給率は、「国家公務員退職手当支給率早見表」にて確認できます。
以下は、看護師の場合の退職手当額の例です。
- 俸給月給:317,928円
- 勤続年数:25年
- 退職理由:定年退職(60歳)
- 支給率:35%
例)退職手当額 = 317,928円×33.3=10,587,002円
退職手当は、国家公務員の退職時に一括で支払われます。
ただし、退職後に別の職場で働く場合などは、一部支給されないこともあります。
地方公務員の退職金
地方公務員の退職金は、地方公務員法に基づいて算出されます。
算出方法は以下の通りです。
- 基本額 = 退職日の給料月額 × 退職理由別・勤続年数別支給率
- 調整額 = 調整月額のうち、60ヶ月分の額を合計した数
これらを合わせて、退職手当額が算出されます。
退職理由別・勤続年数別支給率は、総務省が公表しており、国家公務員と似た方法で算出されますが、地方公務員は調整額がプラスされます。
例えば、地方公務員のAさんが30年間勤務した場合を考えてみましょう。
退職日の給料月額が50万円だとし、勤続年数30年であるとします。
- 基本額 = 50万円 × 退職理由別・勤続年数別支給率(7)= 350万円
- 調整額 = 調整月額のうち、60ヶ月分の額を合計した数(例えば、調整月額が30万円だとすると、30万円 × 60ヶ月 = 1,800万円)
退職手当額 = 基本額(350万円)+ 調整額(1,800万円)= 2,150万円
以上のように、地方公務員の退職金は基本額と調整額の合計額で算出されます。看護師が退職金を増やす4つのポイント
看護師の方々が退職金を増やすためにはいくつかのポイントがあり、その中でも看護師の資格によって退職金の額が異なることがあります。
平均的な退職金の相場と資格によってどのくらい差が出るのか、以下のポイントを説明します。
退職金が高い職場に勤める

看護師が退職金を増やすためには、職場選びが重要です。
具体的には、退職金制度の充実度や企業の財務状況などが退職金額に影響するため、高い退職金が期待できる職場を選ぶことが大切です。
以下は、退職金が高い職場に勤めるための具体的なポイントです。
- 大手病院や公立病院など、大規模な医療機関に就職する
- 企業の財務状況を調べ、財務面が安定しているところを選ぶ
- 労働組合がある場合は、退職金について交渉してもらう
- 退職金制度が充実している職場を選ぶ
これらのポイントを踏まえて、看護師は退職金が高い職場を選び、退職金額を増やせます。
資格を取得する
看護師の資格以外の資格を取得することで退職金が増えることがあります。
医療事務や介護福祉士などの資格が挙げられます。
退職金が増える理由は、資格手当や特別加算が付くためです。
例えば、医療事務の資格を取得すると、月額に5,000円〜15,000円の資格手当が支給される場合があります。
また、介護福祉士の資格を持つ看護師は、退職金の受取額が増えることがあります。
介護福祉士の資格を持つと、介護保険施設での勤務が可能になり介護報酬を得られます。
介護報酬は介護保険から支払われるお金であり、看護師が介護保険施設で働いた場合、退職金が増える可能性があります。
役職に就く
役職に就くことで、賃金が増えるだけでなく、退職金の額も増えます。
具体的には、看護師の中でも<理職に就くことが退職金アップに繋がる>ことがあります。
看護部長や副部長、教育担当などのポジションに就くことで、基本給や賞与がアップし、退職金も増える傾向があります。
ただし、役職に就くためには経験やスキルが必要なため、資格取得やキャリアアップのための勉強などを積極的に行いましょう。
IDECOを活用する
iDeCoとは個人型の確定拠出年金制度であり、自ら運用して将来の年金を準備する仕組みです。
iDeCoを活用することで、自分自身の老後のために資金を確保できます。
以下に、iDeCoを活用するための具体的な方法をご紹介します。
iDeCoに加入する
まずは、iDeCoに加入することが必要です。
iDeCoには自分で運用するタイプと運用を任せるタイプがあり、自分自身で運用する場合は証券会社などに口座を開設してから加入できます。
適切な運用方針を設定する
iDeCoに加入したら、運用方針の設定が大切です。
年金運用は長期的な視点が必要とされますので、適切なポートフォリオの構築が重要です。
具体的には自分自身のライフプランやリスク許容度に合わせて、株式、債券、投資信託などの運用対象や配分比率を決めます。
定期的に積み立てる
iDeCoに加入して適切な運用方針を設定したら、定期的に積み立てることが重要です。
毎月ある程度の金額を積み立てることで、老後の資金をコツコツと貯められます。
以上が、iDeCoを活用するための基本的な方法です。
自分自身のライフプランに合わせてiDeCoを活用し、安心した老後を過ごすための資金を確保しましょう。
看護師の退職金について
よくある質問
ここまで看護師の退職金について詳しく説明してきました。
こちらでは看護師の退職金のよくある質問をQ&A形式で説明いたします。
退職金はいつもらえるの?
退職金は、退職した後に雇用期間や勤務成績に応じて支払われる手当のことです。
退職金の支払い時期は、労働法によって定められています。
一般的には、退職日から2週間以内に支払われることが多いですが、会社によってはもう少し遅れる場合もあります。
ただし、会社が経営難などの理由で退職金を支払えない場合もあります。
その場合は、退職金の支払いが保障される「退職金等支払責任履行事業者」によって、支払われることがあります。
退職金にも税金がかかるの?
退職金にも税金がかかることがあります。
退職金は収入として課税対象ですが、一定の条件を満たす場合は、所得税が軽減される場合があります。<
具体的には、以下のような条件があります。
- 退職年齢が60歳以上であること
- 退職から1年以内に全額を一時金で受け取ること
- 年収が一定額以下であること
退職金にかかる税金は、所得税の他に、住民税や社会保険料もあり、退職金の支給方法によっても税金の計算方法が異なるのです。
自己都合退職の場合であっても看護師の退職金はもらえますか?
自己都合退職の場合でも勤続年数に応じて、一定の退職金が支給される場合があります。
自己都合退職とは、自分自身の都合で退職することです。
具体的には企業によって異なるため、会社の規定によって支給されるかどうかが決まります。
例えば、転職や家庭の事情により退職する場合などです。
ただし、会社によってはどのような理由でも、退職金が支給されない可能性もあります。
看護師の退職金は少ないのでしょうか?
一般的に、看護師の退職金は、他の職種や産業に比べてそこまで多くはありません。看護師の退職金の額は、勤続年数や働く病院の規模や種類によっても異なります。
公立病院や大手私立病院などの大規模な医療機関では、一般に従業員の福利厚生が整っており、退職金の支給額も比較的高いことがあります。しかし、個人病院や小規模な医療機関では、経済的な制約や経営状況の影響で、退職金の支給額が少ないことがあります。
看護師2年目でも退職金はもらえますか?
看護師2年目でも退職金がもらえるかどうかは、勤務先の退職金制度によって異なります。
詳しくは以下の点を確認する必要があります。
勤務先の退職金制度: どの種類の制度を採用しているかを確認しましょう。
支給要件: 勤続年数以外にも、病気や怪我などによる退職の場合に、例外的に支給される場合もあります。
支給額: 勤続年数や退職時の給与などによって、支給額は異なります。
2年目で退職する場合、退職金がもらえない可能性も十分に考えられます。しかし、少額であっても支給される可能性もあります。まずは人事担当者に相談、労働契約書を確認してみましょう。
まとめ
看護師も労働者として、勤務した期間に応じた退職金を受け取れます。
退職金は、一般的には勤続年数や給与水準に応じて算出されるのですが、退職する理由によっては支払われない場合もあります。
看護師の退職金についてのポイントは、以下の通りです。
- 退職金は、勤続年数や給与水準に応じて算出
- 自己都合退職の場合は、勤続年数にかかわらず退職金が支払われない場合がある
- 退職金は、会社が定める規程に基づいて支払われる
- 退職金は、税金がかかる場合がある
看護師のための退職金の受け取り方も合わせて覚えておくと良いでしょう。
- 退職届を提出し、退職日を決定する
- 退職金の額が示された通知書を受け取る
- 銀行口座の情報を提供する
- 会社から退職金が振り込まれるのを待つ
退職金は就業していた期間や退職理由などによって、受け取れる額が異なります。
看護師は自分が所属する会社の規程をよく確認し、退職する際には事前に退職金についての情報を把握しておくことが大切です。
看護師におすすめの転職サイト
参考記事:【看護師向け】おすすめの転職サイト人気ランキング20選を比較|選び方や口コミも紹介
参考文献
この記事の運営者情報
| メディア名 | ミチビーク |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社Method innovation |
| 会社ホームページ | https://www.method-innovation.co.jp/ |
| 所在地 |
〒550-0013
大阪府大阪市西区新町3丁目6番11号 BADGE長堀BLD. 2階
|
| 代表取締役 | 清水 太一 |
| 設立 | 2016年11月1日 |
| 事業内容 | 集患支援事業 メディア運営事業 広告代理店事業 |
| お問い合わせ | michibi-Qのお問い合わせはこちら |