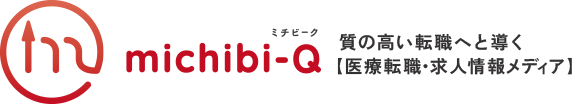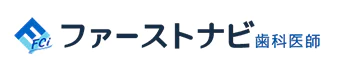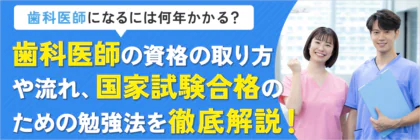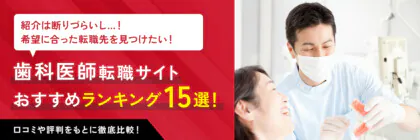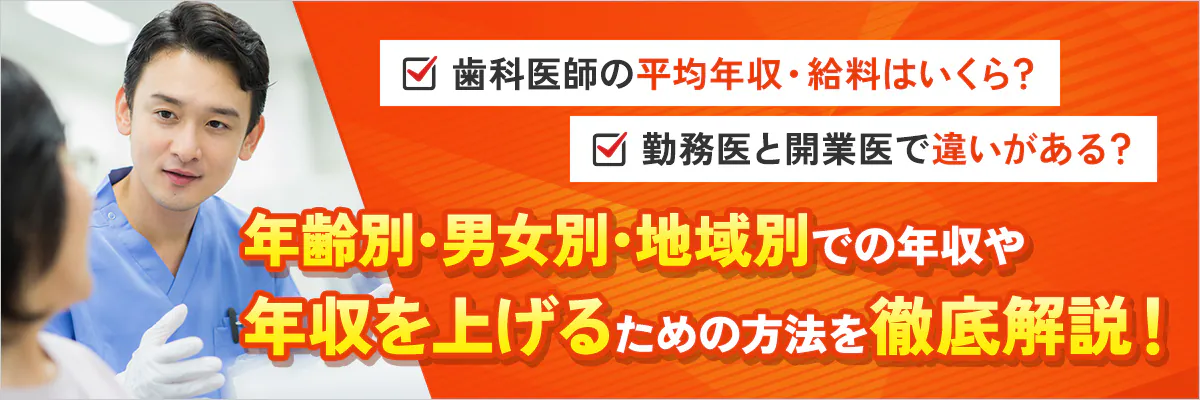
※当サイト(ミチビーク)はアフィリエイト広告を掲載しています。
この記事の監修者

みやけ歯科医院
理事長 三宅 勝俊
【経歴】
1984年に大阪歯科大学を卒業し、歯科医師免許を取得した後、心斎橋の歯科医院に勤務。1990年に大阪市都島区にみやけ歯科医院を開院。2016年に医療法人優俊会を設立。また2017年に分院のワハハキッズデンタルみやけ歯科を開院。『自分自身が受けたい治療を患者様に提供する』モットーに日々患者さんと向き合い、地域の方のお口と身体の健康を支えている。
【資格】
歯科医師
日本メタルフリー歯科学会 認定医
医療法人優俊会 みやけ歯科医院 ホームページ
https://www.miyake-shika.com/

【経歴】
大学卒業後、ウェディングプランナーとして営業職を経験し、24歳からITベンチャー企業の人事部にて採用・教育などの仕事に従事。採用は新卒・中途の営業職から事務職、クリエイティブ職など幅広い職種の母集団形成から面接実施、内定者フォロー、入社手続き等を行い、教育では研修コンテンツ企画、資料作成、講師育成までを実施。人材開発部立ち上げや、社内の人事評価、従業員満足度調査、社員のメンタルケアなども行っていた。それらの経験を経て、さらに専門性を高めるためにキャリアコンサルタントの資格を取得。
現在も今までの経験・知識を活かしつつ、二児の子育てと両立させながら、株式会社Method innovationのグループ会社である株式会社ドクターブリッジにて人事の仕事に従事している。
【資格】
キャリアコンサルタント
アロマテラピー検定1級
プラクティカルフォト検定1級
ファッションビジネス能力検定1級
ファッション販売能力検定1級
【歯科医師におすすめの
転職サイト3選】
さらに参考記事:【歯科医師向け】おすすめの転職サイト・エージェントランキング15選を徹底比較|選び方も解説!の記事もぜひご覧ください!
歯科医師などの医師は、医療従事者の中でもとりわけ給料が高いと考えている人もいらっしゃると思います。
歯科医師には勤務医や開業医など働き方は複数あり、その働き方次第で年収にも差があります。
以下では、歯科医師の年収や月給、勤務医と開業医の違い、年収アップのための方法などを最新の情報に基づいて丁寧に説明いたします。
歯科医師の平均年収について

歯科医師の給料は高いと考えている人は多くいると思いますが、では具体的に歯科医師の平均年収はどれくらいなのかを以下で詳しく説明していきます。
歯科医師の平均年収は減ってきている
| 年収 | |
|---|---|
| 男性 | 794万1千円 |
| 女性 | 878万2千円 |
| 男女計 | 811万円 |
※参考文献:令和4年 賃金構造基本統計調査 職種|厚生労働省
厚生労働省の調査によると、令和4年度の歯科医師の平均年収は811万円となっており、一般的なサラリーマンの平均年収443万円よりも非常に高くなっています。
一方で、1990年代後半から比べると、歯科医師の平均年収は少しずつ下がっていると言われています。
理由としては、患者の数に対して歯科医師の数が多くなっていることが挙げられます。
昭和の時代は患者に対して歯科医師の数が足りなかったため、政府主導で新しい歯学部を増やすなどの施策が推進されてきました。
しかし、フッ素などの虫歯予防が当たり前になって歯科の患者は以前よりも少なくなっており、今度は歯科医師の数が患者に対して多すぎる状況となっているのです。
参考文献:国税庁「令和3年民間給与実態調査」
歯科医院はコンビニより多いって本当?

1950〜60年代の日本では、国民の30%が虫歯になっていたと言われるほど、非常に多くの虫歯患者がいました。
そのため、政府が主導して、歯科医師の人数を当時の人口10万人に対して35人→50人に増強する施策が行われていました。
具体的には、様々な大学で新しく歯学部が設立されたり、新しい歯科大学が設立されたりするなどしたことで、1960年代は約1,100人だった歯学部の入学定員が10年で約3,500人にまで増加し、歯科医師の数が大きく増えることとなりました。
しかし、フッ素などの虫歯予防が当たり前になったことで歯科医院の患者数は少なくなってきましたが、歯学部の入学定員は同じ水準のままとなっていたため、歯科医師の数が多すぎる状況となってしまいました。
現在、歯科医師は人口10万人に対して80人以上いると言われており、コンビニを超えるほどの多くの歯科医院が町中に存在しています(コンビニの数(2023年4月時点):55,759店に対して、歯科医院の数(2023年3月時点):67,761軒となっています)。
※参考文献:コンビニエンスストア統計調査月報|日本フランチャイズチェーン協会
※参考文献:医療施設調査・病院報告|厚生労働省
開業医と勤務医の差

歯科医師だけの話ではありませんが、医師は勤務医もしくは開業医として働くこととなります。
勤務医・開業医でどの程度年収に違いがあるかについて以下で説明いたします。
| 平均年収 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 開業医 | 587万円 | |||
| 勤務医 | 一般病院 | 1,156万円 | ||
| 歯科診療所 | 院長 | 1,475万円 | ||
| (医療法人) | 歯科医師 | 746万円 | ||
※参考文献:第23回医療経済実態調査(2021年)|中央社会保険医療協議会
開業医として働く場合の平均年収は587万円となり、そこまで高いとは言えません。
人口減少が続いており歯科医院の患者も多くない地域で開業すると年収は低くなりやすいです。
また上記の通り、全国的に歯科医院の数が多すぎる状況も相まって年収が低くなっていると想定されます。
一方で、歯科診療所(医療法人)の院長となれば、年収は約1,400万円と相応に高い水準となります。
なお、歯科医院の開業には莫大な費用が必要となり、開業後も一定のランニングコストが発生するため、開業したら必ず高年収となるというものではありません。
開業するには5,000万円程度の費用が必要
歯科医院の開業資金としては、医院の規模によっても変動しますが、ユニット3台程度の施設であっても少なくとも5,000万円は必要となると言われています。
具体的に発生する費用としては以下の通りです。
①物件費
戸建て、居抜き、テナントなど物件の条件によっても異なりますが、物件費が開業にあたって一番大きな費用となります。
都心部・郊外など開業する場所によっても違いはありますが、少なくとも3,000万円(テナントの場合:500万円)は必要となります。
②内装工事費
テナントの場合は少なくとも1,500万円はかかると思います。
内装に拘りすぎるとその分初期費用が大きくなってしまうため、居抜き物件なども候補に入れることをおすすめします。
③広告宣伝費
新規の患者を集めるためにも開業半年以前から作成しておくことが大切です。
具体的には、HPを作り、Google検索などでヒットしやすくなるための対策(SEO対策)を重視することをおすすめします。
なお、最低限の構成であればHPは20万円程度で作ることができますが名刺変わりぐらいになるので、そんなに効果は得られない可能性があります。
④医療機材・設備費
導入する設備の種類によっても違いがありますが、少なくとも2,000万円は必要になると考えておいてください。
具体的には、ユニット1台で約250〜500万円、エアーコンプレッサーやバキュームなども加えると、それぞれ約50万円は追加で必要となります。また、モニター、CT、デジタルレントゲン、光照射器、超音波洗浄機、滅菌機、レセコンシステムなども開業にあたって必要となります。
なお、これらの機材を全て最新のもので揃えようとすると、トータルで約2,500万円は必要になると思います。
他にも、アルジネート印象材、麻酔薬、ディスポ消耗品などを準備しなければなりません。
開業したら絶対に高年収が約束されるというものではありません。
医院の立地に問題があり患者を増やせなかった、近隣の歯科医院に患者を取られてしまったなどの理由で、開業してすぐに廃業する医院も少なくないのが実情です。
成功すれば高い年収が期待できますが、初期投資がかなり大きいことはもちろん、開業後も乗り越えなければならない課題がたくさんあるため、それを踏まえて慎重に検討することをおすすめします。
開業するタイミング・年齢について
歯科医師は、35〜36歳で約17%、50代までに約70%が開業すると言われています。
開業する年齢には個人差がありますが、40〜50代までに開業する人がほとんどです。
開業する平均年齢は41.3歳というデータもあり、開業を考えている方は参考にしてみてください。
詳しいデータについては、以下の表をご参照ください。
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 1% | 24% | 67.2% | 82.2% | 87.1% | 75.1% | 50.4% |
| 女性 | 0.3% | 5.7% | 21.4% | 35% | 45.5% | 47.1% | 36.6% |
| 全体 | 0.7% | 17.4% | 53.3% | 73.2% | 81.1% | 72.5% | 48.7% |
参考文献:平成30年(2018年)医師・歯科医師・薬剤師統計
上記の表によると、60代で開業する人が一番多く、50代、70代と続きます。
一方で、開業が増えそうな30代の人はそこまで多くないということが分かります。
これは、開業のために莫大な初期費用が必要なことと、独立してやっていけるくらいのスキルはこの年代ではまだ身に付かないためだと想定されます。
しかし、最初から開業する前提でスキルの習得や資金調達の準備を前倒しで進めておくと、若い年代でも開業して成功できる可能性はあります。
歯科医院を開業するベストな時期はいつ?
ベストな時期は一概には言えませんが、「開業資金の目途が付いた時」「ライフステージが変化した時」「独立してやっていけるくらいのスキルを習得できた時」などで開業を考える人が増える傾向にあります。
「〇〇歳で開業すれば必ずうまくいく」という保証はないため、開業資金、自分の知識や技術などを考慮して自分に合ったタイミングで開業を考えることをおすすめします。
歯科医院を開業したい人は早い段階から準備しておくことがおすすめです。
歯科医院を開業したいと考えている人は、なるべく早い段階から準備することをおすすめします。
早い段階から準備できれば、条件に合った物件を見つけたタイミングなどですぐに動くことができます。
「良いタイミングが来たら考える」「〇〇歳になったら考える」といったように後手に回ってしまうと、本当に良い物件が見つかったタイミングなどで積極的に動けず、他の人に先を越されてしまう可能性もあります。
勤務医は勤務先によって年収に大きな差が出る
勤務医として働くと、平均年収は歯科診療所で746万円、一般病院で1,156万円と1.5倍ほどの差が生まれます。
これは、勤務先の規模や経営状況などによって、給与に差が出るためだと想定されます。
そのため、勤務医として働く際は、歯科以外の診療科もあるような大規模な病院で勤務する方が高年収となる可能性が高いでしょう。
歯科診療所と一般病院の違い
- 歯科診療所
以下の一般病院の定義に該当しない医療施設のことで、医師が最低1名いることを除き人員の条件はありません。 - 一般病院
患者が20名以上いる入院可能な医療施設のことです。
医師だけでなく、薬剤師や看護師などについても最低人員の条件があります。
具体的に勤務先の規模による差はどれくらい?
厚生労働省の令和2年賃金構造基本統計調査による規模別で見た平均年収については、従業員1,000人以上の大規模施設が982万8,900円、従業員5~9名の小規模施設が962万7,600円と相応に高い水準である一方で、従業員100〜999人規模の施設では639万4,200円と低い水準となっています。
歯科医師の年齢による年収の差
| 年齢 | 平均年収 |
|---|---|
| 25~29歳 | 557万7,200円 |
| 30~34歳 | 666万2,600円 |
| 35~39歳 | 523万8,700円 |
| 40~44歳 | 978万7,600円 |
| 45~49歳 | 969万6,800円 |
| 50~54歳 | 1140万5,100円 |
| 55~59歳 | 1156万9,200円 |
| 60~64歳 | 883万5,100円 |
| 70歳以上 | 1483万8,000円 |
男性では40代後半が、女性では50代後半が最も年収が高い年代となります。
また、歯科医師は定年制ではないため、60代を超えても一定の収入を稼いでいる人が多数存在します。
なお、歯科医師として働くためには、歯学部を卒業して資格を習得してから臨床研修を1年以上受けることが求められます。
そのため、研修期間にあたる24歳の年収は210万円程度となり、全職種の平均年収443万円の半分以下とかなり低くなりますが、年齢を重ねていくにつれて年収は上がる傾向にあります。
歯科医師の男女による年収の差
| 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
|---|---|---|---|
| 男性 | 約831万円 | 約874万円 | 約794万円 |
| 女性 | 約676万円 | 約538万円 | 約878万円 |
参照:賃金構造基本統計調査 7 職種(特掲)、性、年齢階級別きまって支給する現金給与額
賃金構造基本統計調査 / 令和4年賃金構造基本統計調査(順次掲載予定) 一般労働者 職種
男性は令和2年度~令和4年度の間に年収は下がっている一方で、女性は約200万円上がっています。
厚生労働省による令和2年 医師・歯科医師・薬剤師統計によると、2020年年末次点の歯科医師の数は10万7,443人(男性8万530人、女性2万6,913人)となっています。
男女比は、男性:女性=7:3となっており男性の方が圧倒的に多い状況です。
また、日本歯科医師会が行った調査結果では、子どもを持つ女性の歯科医師で過去に離職経験がある人は約6割いるとされています。
女性は一度離職してから、アルバイトやパートとして勤務する、もしくは有休を取りやすい職場を選ぶといった人が多い傾向にあります。近年の歯科医師国家試験の合格者の4割以上は女性であり、今後も女性の歯科医師は多くなっていくと考えられます。
そのため、出産してからも職場復帰しやすい環境を構築するだけでなく、診療所に保育施設や託児所を併設するなど、子育てをする女性に優しい職場作りが重要になってくるでしょう。
歯科医師の地域による年収の差
求人ボックスの統計データによると、平均年収は関東が一番高く、特に東京都が高い水準(425万円)となっています。
一方で、青森県が一番年収の低い(283万円)地域となっており、東京都と比べると142万円の差があります。
歯科医師の仕事条件による年収の差
求人ボックスの統計データによると、全体と比べて「教育担当」(+5%)「分院長」(+29%)となっており、他の職種と同様にリーダー的な役割やマネジメント層になると給与が高くなる傾向にあります。
歯科医師の平均月給について
| 組織規模 | 5〜9人 | 10〜99人 | 100〜999人 | 1,000人以上 |
|---|---|---|---|---|
| 月給
(手当なし) |
75万7,600円 | 58万1,200円 | 46万7,300円 | 68万7,800円 |
| 月給
(手当あり) |
76万4,700円 | 58万9,200円 | 49万3,400円 | 71万9,600円 |
| 平均年齢 | 51.2歳 | 39.9歳 | 38.2歳 | 40.4歳 |
 参考文献:厚生労働省 令和2年賃金構造基本統計調査
参考文献:厚生労働省 令和2年賃金構造基本統計調査
歯科医師の平均月給(組織規模問わず)は59万4,800円となりますが、この中には残業代などの手当として約1万7,000円が含まれています。
また、実際に支給される金額は、ここから社会保険料や所得税などを控除した金額です。
給料が歩合制で働く歯科医師もいる

歯科医師の中には、毎月決まった給料で働いている人の他に、歩合制で働いている人もいます。
自分が担当した診療売上の数%を給料としてもらう形となり、自分のスキルや実際の業務量に応じて毎月の給料が上下するため、高いモチベーションを保って働くことができます。
また、固定給に歩合給をプラスして支給する歯科医院も存在します。
歯科医師の賞与・ボーナスについて
| 組織規模 | 5〜9人 | 10〜99人 | 100〜999人 | 1,000人以上 |
|---|---|---|---|---|
| 賞与・ボーナス | 45万1,200円 | 67万4,900円 | 47万3,400円 | 119万3,700円 |
| 平均年齢 | 51.2歳 | 39.9歳 | 38.2歳 | 40.4歳 |
 参考文献:厚生労働省 令和2年賃金構造基本統計調査
参考文献:厚生労働省 令和2年賃金構造基本統計調査
従業員10人以上の組織におけるボーナス・賞与の平均支給額は73万7,500円となります。
支給額は施設の経営状況によって左右されるため、特に従業員1,000人以上の大規模施設の平均は119万3,700円となっており、かなり高い水準と言えます。
歯科医師の時給について
| 組織規模 | 5〜9人 | 10〜99人 | 100〜999人 | 全事業者平均 |
|---|---|---|---|---|
| 時給 | 5,705円 | 2,994円 | 3,410円 | 5,314円 |
 参考文献:厚生労働省 令和2年賃金構造基本統計調査
参考文献:厚生労働省 令和2年賃金構造基本統計調査
全事業者の平均時給は5,314円となり、専門的な技術が求められる仕事であることから、一般的なパートアルバイトの時給よりかなり高い水準だと言えます。
公務員として働く歯科医師の
平均年収について
医師・歯科医師の地方公共団体職員平均給与額
| 給料月額 | 49万6,013円 |
|---|---|
| 扶養手当 | 1万964円 |
| 地域手当 | 6万260円 |
| 平均基本給月額 (合計) |
56万7,237円 |
 参考文献:厚生労働省 令和2年賃金構造基本統計調査
参考文献:厚生労働省 令和2年賃金構造基本統計調査
公務員として働く歯科医師の平均月収は56万7,237円となっています(地域手当や扶養手当を含む)。
また、「特殊勤務手当」(特別な手当が必要な困難や危険が起こる可能性がある勤務に支給されるもの)や「初任給調整手当」(僻地勤務となる場合に支給されるもの)を含めると、月給が108万6,014円と高い水準となります。
国家公務員(医系技官)の場合
国家公務員として働く歯科医師は、「医系技官」として高い技術や知識をもとに保健医療に関係する研究、政策の立案・実施、厚生労働省の関係機関での勤務などを行います。また、国営の医療機関で働くこともあります。
国家公務員として働く歯科医師の給料は、法律に基づき「俸給表」に従って支給額が決められます。
具体的な支給額は以下のようになります。
医療職俸給表(一)
| 平均給与月額 | 840,532円 |
|---|---|
| 俸給 | 507,742円 |
| 地域手当など | 90,890円 |
| 俸給の特別調整額 | 34,536円 |
| 住居手当 | 6,304円 |
| 扶養手当 | 10,851円 |
| その他 | 190,209円 |
参考文献:令和4年国家公務員給与等実態調査
国家公務員として働く医師や歯科医師は「医療職俸給表(一)」が該当し、高い技術や豊富な知識が求められる職業であるため、平均年収は1,370万円程度となり、他の国家公務員と比べても高く設定されています。
地方公務員の場合
地方公務員として働く歯科医師の場合、各地方自治体の公立病院のスタッフ、もしくは自治体職員として働くこととなります。
地方公務員として働く場合の給料は各自治体の「給料表」に則って支給されますが、一般的に国家公務員よりも少ない傾向にあります。また、民間のクリニックや病院と比較しても、年収の水準が低いと言われています。
なお、公務員として働くことは、ボーナスなども込みで収入が安定していることや福利厚生も完備されている点がメリットとして挙げられます。
正社員以外で働く場合
非常勤の場合
非常勤の場合は、実際に勤務した日数や時間に応じた給与が支給されることがほとんどです。
時給制となる場合がほとんどですが、医療機関によっては週給や日給となることもあります。
非常勤は常勤よりも勤務時間や日数が少なくなりがちであり、その分給与も少なくなります。
しかし、勤務時間や日数を柔軟に設定可能なため、ワークライフバランスを意識した働き方が可能となるメリットがあります。
また、非常勤で働く歯科医師はいくつかの歯科医院を掛け持ちで働いている人も少なくありません。
そうすることで、収入アップはもちろんのこと、様々な症例や診療を経験することで技術の向上に繋がる可能性があります。
派遣社員の場合
派遣社員として働く場合は、紹介予定派遣がほとんどです。
日本の法律では医師の労働派遣がNGであるため、紹介予定派遣として派遣先の医療機関で数ヶ月間勤務した後に正社員として登用されることとなります。
派遣社員として働く方法を選ぶ人は、生活習慣に応じてフレキシブルに働きたい、働ける時間や日数が制限されているといった背景となっていることがほとんどです。
通常の派遣社員とは違い、歯科医師などの国家資格や高度なスキル、ノウハウが求められる職種の時給は高い水準となっていることがほとんどで、中には3,000円を超えるような求人も存在します。
なお、歯科医師の求人は通常の医療機関の求人よりも珍しく、自分に合った条件の求人を見つけることはそう簡単ではないかもしれません。
歯科医師の福利厚生について
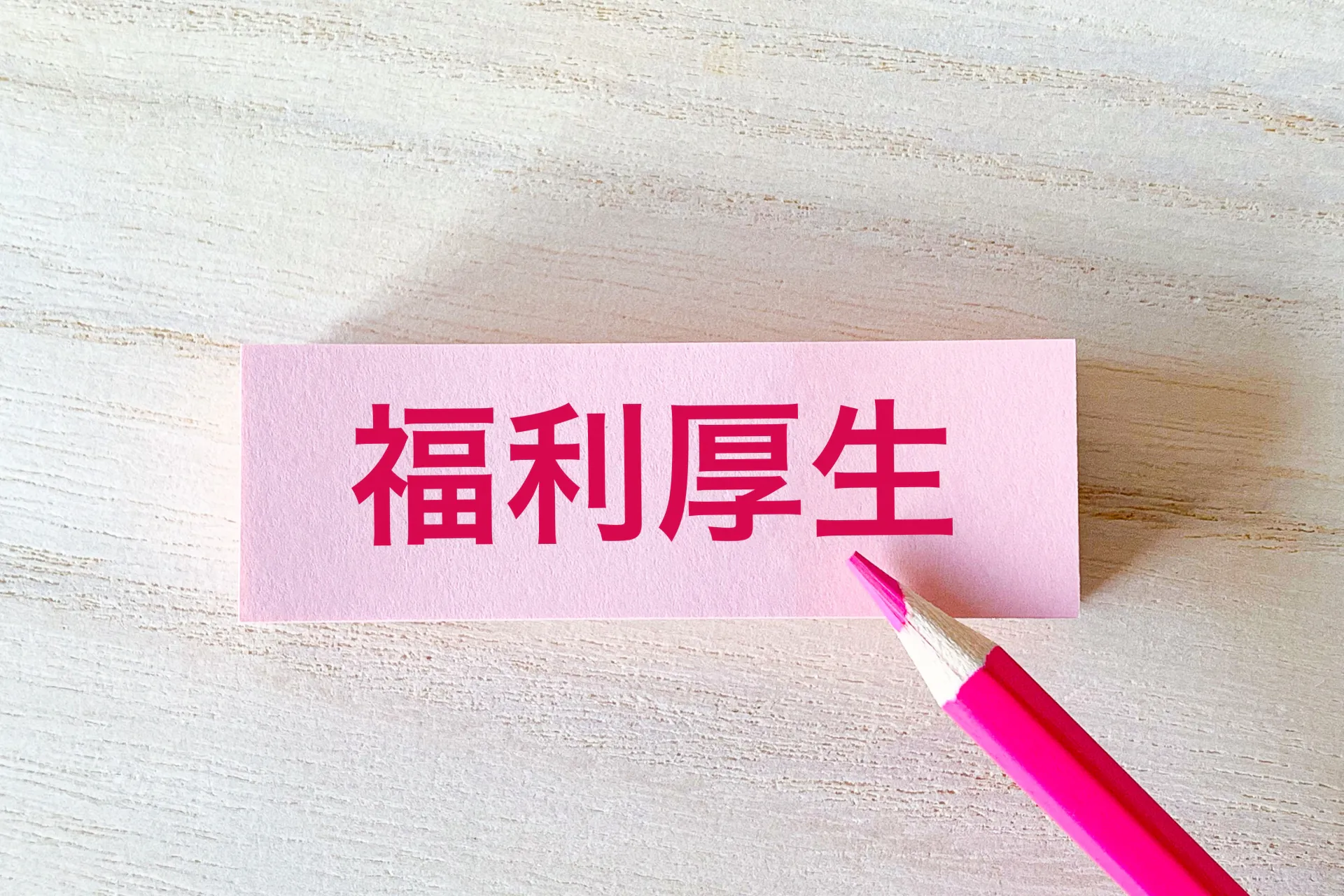
歯科医師の勤務先は多岐にわたりますが、福利厚生がどれくらい整っているかは勤務先によってまちまちです。
大規模な大学病院や総合病院、大手法人が経営するクリニックでは、一般企業と遜色ない福利厚生があることがほとんどです。
具体的には、各種社会保険や住宅手当、通勤手当、家族手当などの基本的な福利厚生の他、健康診断、保育所の利用、退職金制度、資格取得支援制度など様々な制度があり、歯科医師が就業しやすい環境となっています。また、地域に根付いた歯科クリニックも十分な福利厚生があるところが多い傾向にあります。
その他、こうした制度だけでなく、連続して有休を取得できるかについても確認しておくと良いでしょう。
歯科医師になる方法

歯科医師になるための一般的な方法としては以下の通りです。
- 歯学部で6年間の専門課程を修了する
- 歯科医師の国家試験に合格する
- 1年間の臨床研修を終える
また、海外の大学の歯学部を卒業して歯科医師国家試験の予備試験に合格し、診療や口腔衛生に関わる実地訓練を1年以上受けている場合は、歯科医師の国家試験を受けることが可能です。
歯科医師の国家試験とは
歯科医師の国家試験は、毎年1月下旬あるいは2月上旬に1回だけ行われ、3月中旬には合否が分かります。
試験では、臨床で欠かせない歯科医学や口腔衛生に関する歯科医師が習得しなければならないスキルや知識の問題が出題されます。
配点は、必修問題が出される一般問題が1問1点、臨床実地問題は1問3点となります。
歯科医師の国家試験は年々難しくなっている
歯科医師の国家試験は近年難化傾向にあります。
これは、歯科医師の数と患者の数のバランスを維持するために、文部科学省と厚生労働省が2006年に協議した結果、歯科医師の数を減らす方向となったことが背景にあります。
2006年の歯科医師の国家試験は合格率80.8%、2007年は74.2%とそれなりに合格しやすい試験でした。
しかし、ここ数年は合格率が下がっており、2023年の試験は合格率63.5%となりました。
未だに歯科医師の数が患者に対して多すぎる状態は変わっていないため、当分は国家試験の難易度が下がることはないと推測されます。
国家試験を受験するには歯学部を卒業する必要がある
歯科医師国家試験の受験にあたっては、歯科大学や歯学部を卒業することが基本条件となります。
その他の詳しい条件は次のようなものがあり、以下の4つの中で1つでも該当すれば受験することができます。
- 歯学部や歯科大学で歯学についての専門課程を終了した人
- 歯科医師国家試験予備試験に合格し、診療や口腔衛生についての実地修練を1年以上受けた人
- 海外の歯科医学校を卒業もしくは海外で歯科医師免許を取得した人の中で、上記1.2.と同じくらいのスキルや知識を有していると厚生労働大臣から認められた人
- 沖縄の日本への返還前に琉球政府の歯科医師法に基づき歯科医師免許を交付された人の中で、厚生労働大臣から認められた人(沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号)第18条第1項の規定に基づく)
歯科医師国家試験に合格した人には、歯科医師免許が交付されます。
また、それに合わせて「衛生検査技師」「衛生管理者」「食品衛生管理者」の資格も手にすることができます。
そして、歯科医師国家試験に合格してから、研修施設として指定された診療所や病院で臨床研修を1年以上受けて開業医や勤務医として働くことが可能になります。
歯学部の学費は3000万円以上って本当?
国公立大学の6年間の授業料は350万円程度である一方で、私立大学の授業料は平均して2,000〜3,000万円程度とかなり差があります。
さらに、授業料だけでなく教材費の負担も発生するため、私立大学に通うとなると6年間のトータルの学費は数千万円にもなります。国内で歯科医師の専門課程がある大学は、国立11校、公立1校、私立15校の合計27大学29学部(日本歯科大学と日本大学がそれぞれ2学部)が存在します。
中でも国公立大学は学費が安いため、非常に競争が激しくなっています。
一方で、私立大学は総じて志願者が減っている傾向にあり、中には定員割れしている大学もあります。
歯科医師として成功するための
2つの方法

歯科医師として成功するにあたり、高い収入を得ることを目指すのであれば、勤務医ではなく開業医としてのキャリアを選ぶこともおすすめです。
開業医として成功するには、歯科医師としての高い技術は当然のこと、経営能力も磨くことが重要であり、特に新規の患者を集めるための戦略を立てるためにマーケティングスキルを習得する必要があります。
そこで、以下では開業医として成功するための具体的な方法を2つ紹介いたします。
マーケティング戦略を強化する
歯科医院をうまく経営するためには、新規の患者をいかに集められるかが重要であり、マーケティング戦略の強化が必要と言えます。
その際、全てを内製化するのではなく、一部を専門業者に外注することも選択肢として考えると良いと思います。
例えば、HP作成や予約システムの開発などを外注することで、より集患に繋がりやすいものを準備できる可能性があります。
なお、外注先の選定にあたっては、歯科医院のマーケティング強化の実績がある業者を複数ピックアップして、しっかりと比較検討することをおすすめします。
人脈やスキルを強化する
経営スキルを磨くためには、勤務医として働いている時から歯科医師としての技術向上に励むと同時に、既に開業している先輩医師や医療機器メーカーの担当者などと定期的に交流することで、開業に向けた情報を集めることをおすすめします。
ある程度の人脈が形成できると、開業する場所はどこが良いか、どの医療機器メーカーに相談すべきか、歯科医院の経営に活かせるノウハウはあるかなど、有効な情報を多方面から集めることが可能となり、歯科医院の経営を成功させやすくなります。
歯科医師が年収を上げる3つの方法

歯科医師が年収アップを目指すには次の3つの方法が考えられます。
なお、どの方法も歯科医師としての技術や経験が前提として求められる点は理解しておく必要があります。
勤務医としてのキャリアアップを目指す
歯科医院の勤務医として収入アップするためには、歯科医師としての技術の向上とキャリアアップが必要です。
例えば、自費診療に対応できるようになったり、分院長に昇格することを目指すなどが有効です。
自費診療は医療費が高額となりやすく、その分収入も上がりやすくなります。
また、分院長まで昇格すると役職手当が支給されて収入アップに繋がることがほとんどです。
自費診療に対応できるようになる
歯科医師として収入アップを目指すには、保険診療ではない自費診療を多く対応することが重要です。
保険診療は患者にとっては医療費の負担が少ないですが、歯科医院側の利益率は低くなります。
一方で、自費診療では保険適用外の高額な医療機器などを使用するため、歯科医院にとっては大きな収入源となります。
なお、患者にとっては医療費の負担が大きくなるため、自費診療が必要な理由や保険診療と比較した際の利点などをしっかりと説明し、理解してもらうことが大切です。
分院長になることを目標とする
歯科医院の分院長の平均年収は約1,475万円とかなり高い水準です。
分院長になると院長として様々な経験を積めるだけでなく、経営者と比べると収入が経営状況に依存することは少ないため、ある程度は安定した収入が期待できます。
また、分院長はマネジメント層として部下の管理が求められるため役職手当が支給されることがあり、通常の勤務医よりも収入が高くなることがほとんどです。
年収が上がる勤務先に転職する
年収アップのためにより多くの患者がいる勤務先に転職することも選択肢の一つです。
患者が多ければ多いほど、自費診療に対応できるチャンスも増えるため、その分収入アップが期待できます。
転職を検討する上では、「患者のニーズを満たせる職場かどうか」を重点的に確認することをおすすめします。
具体的には、高齢者が多く住む地域ではインプラントや入れ歯のニーズが多くあると思います。
そうしたニーズにしっかりと対応できる技術や実績を持つ歯科医院で働くことで、自ずと収入アップの道も開けると考えられます。
「自分だけでは不安」「仕事しながら見つけられるのは大変」という方は転職エージェントの活用がおすすめです。
転職エージェントは求職者の希望から条件のある職場をピックアップしてくれるので、「年収アップ」の条件を伝えておけば、自分で探すよりも効率良く転職が進められます。
開業医になる

開業医になることも収入アップの方法の一つです。以下では、開業医になる2つのメリットと開業医として年収1億円を達成するためにすべき3つのことを説明いたします。
開業医になる2つのメリット
開業医になるメリットとしては次の2つがあります。
- 頑張った分だけ収入が増え続ける
- 自分で治療方針を選択できる
まず、収入については、勤務医のように毎月決まった給料が支給される訳ではないため、医院の経営に成功すればその分高い収入が期待できます。
また、勤務医は勤務先の方針に沿って治療を進める必要がありますが、開業医は自分で治療方針を選択することができるため、自分の考えに基づいて自由に治療方針を検討可能です。
開業医として年収1億円を達成するためにすべき3つのこと
開業医として年収1億円を達成するということは、歯科医師の平均年収の10倍以上を稼ぐこととなり、そう簡単なことではありません。
しかし、以下のようなポイントを意識して絶えず創意工夫と研鑽を続けることで、年収1億円に届くことも期待できますので、参考にしてみてください。
- 新規の患者を一人でも多く集められるようマーケティングを強化し、受け入れ可能な体制を構築する
- 歯科医師やスタッフの採用を強化し、教育とマネジメントの体制を構築する
- 自費診療を一件でも多く対応できるようにする
まとめ
このページでは、歯科医師の年収や月給、勤務医と開業医の違い、年収アップのための方法などについて解説してきました。
歯科医師としてどのようにキャリア形成や年収アップを目指すかは、人によって様々な方法があります。
今回紹介した内容を参考にして、ご自身のライフスタイルやご希望に合った納得できるやり方で、今後のキャリア形成や年収アップについて考えて頂けますと幸いです。
【歯科医師におすすめの
転職サイト3選】
参考記事:【歯科医師向け】おすすめの転職サイト・エージェントランキング15選を徹底比較|選び方も解説!の記事はこちら
参考文献
コンビニエンスストア統計調査月報|日本フランチャイズチェーン協会
第23回医療経済実態調査(2021年)|中央社会保険医療協議会
賃金構造基本統計調査 7 職種(特掲)、性、年齢階級別きまって支給する現金給与額
この記事の運営者情報
| メディア名 | ミチビーク |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社Method innovation |
| 会社ホームページ | https://www.method-innovation.co.jp/ |
| 所在地 |
〒550-0013
大阪府大阪市西区新町3丁目6番11号 BADGE長堀BLD. 2階
|
| 代表取締役 | 清水 太一 |
| 設立 | 2016年11月1日 |
| 事業内容 | 集患支援事業 メディア運営事業 広告代理店事業 |
| お問い合わせ | michibi-Qのお問い合わせはこちら |